結婚式などの祝い事にはご祝儀を頂きますが、皆さんは、手元に残ったご祝儀袋をその後どうしていますか?
処分してしまうのは、「頂いた方に失礼ではないか」「縁起が悪いのではないか」とおもって処分できずにとりあえず保管している人も多いのではないでしょうか。
本記事では、ご祝儀袋の処分方や保管法を5つ紹介しています。この記事を読めば眠っているご祝儀を後悔せずに処分できるでしょう。
可燃ごみとして捨てる
基本的にご祝儀袋は、『もえるゴミ』として処分することが可能です。
ご祝儀袋の内袋にはいただいた方の名前などの個人情報が記載されているので、シュレッダーにかけたり、ペンで塗りつぶすなどしてから処分するようにしましょう。
他の家庭のゴミと一緒に処分するのは気が引けるという方は、紙袋に入れたり新聞紙などで丁寧に包んでから、ごみ袋の一番上にそっと置いて捨てるとよいでしょう。
当然かもしれませんが、中身を取り出してすぐにごみ箱へ捨てたり、他のゴミに埋もれるように無造作に捨てるのは、相手の厚意を踏みにじるような行為のためマナー的にもよくありません。
神社でお焚き上げをしてもらう
自分で処分するのが心苦しいという方は、神社やお寺で「お焚き上げ」をしてもらうのがおすすめ。
お焚き上げとは、粗末に扱うことができない神仏にかかわるものや、思いがこもっていて捨てるのが忍びないものなどを、感謝の気持ちを込めて供養することです。
お守りやお札とは異なるため必ずしもお焚き上げが必要ではないですが、気持ちに整理をつけるために、お焚き上げをしてもらう方もいらっしゃいます。
神社やお寺によっては、社務所にお焚き上げ等の御守・御札等を納める箱があり、年末年始だけでなく通年を通して納めることができます。
ただし、諸事情によりお焚き上げできるものを限定している神社やお寺もありますので、事前にご祝儀袋のお焚き上げもやってくれるかどうか確認した上でだすようにしましょう。
郵送型のお焚き上げサービスを活用
「忙しくて持ち込む時間が取れない」「近所にご祝儀袋のお焚き上げを受け付けている神社やお寺がない」という方は、郵送型のお焚き上げサービスを利用してみるのはどうでしょうか。
神社やお寺に頼むより費用は高くなりますが、燃えないゴミも含めて大抵の物は受け入れてもらえるのが利点です。オンラインでいつでも申し込めるため、神社やお寺に直接お願いするよりもスムーズかもしれません。
連携している由緒ある神社でお焚き上げした後は、証明書が発行されるなど、祈祷後のフォローも万全のため安心して利用することができます。
実績10,000人以上、顧客満足度96%の「みんなのお焚き上げ」
デジタルな思い出まで幅広く供養できる「お焚き上げ神事.com 」
リメイクする
最近は凝ったデザインのおしゃれなご祝儀袋も増えていて、そのまま処分するのはもったいないという人は、思い切ってリメイクしてみてはいかがでしょうか。
ブックカバー、箸袋、リース・アクセサリーなど身近なアイテムにリメイクして活用することで、大切な思い出をいつでも振りかえることができるのでおすすめです。
インスタグラムやツイッターで「ご祝儀袋 リメイク」などと検索すると素敵な作品がたくさん出てくるので是非参考にしてみてください。
宅配型トランクルームを利用する
すぐに捨てるという判断ができない場合には、とりあえずトランクルームで保管するというのもありですよ。
「宅配トランクルーム」は段ボール単位で荷物を保管してくれる収納サービスで、小さなものやほんの少しだけ預けたい人にピッタリのサービスです。
利用者が荷物を預けに行くトランクルームとは違い「荷物の集荷」「管理」「出し入れ」すべてがスマホ操作でできてしまいます。
基本的にどのサービスもダンボール1箱あたりの月額保管料が500円以内とリーズナブルなので気軽に利用することができます。
ご祝儀袋の処分法と保管法まとめ
もともと、「ご祝儀袋」は、中の贈り物が清浄なものであるという意味を込めて、真っ白な和紙で包んだとされています。
つまり、ご祝儀袋は単なる入れ物にすぎないので、あまり神経質に考える必要はありません。
あなたが受け取った時点でご祝儀袋としての役目は終わっているので処分してもまったく問題ないということです。
ご祝儀袋の処分方法については正式なルールや決まった作法などはないので、自分自身が納得できる方法を選択されると良いでしょう。

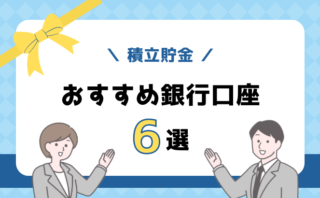
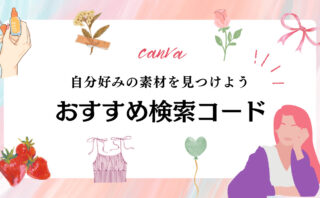
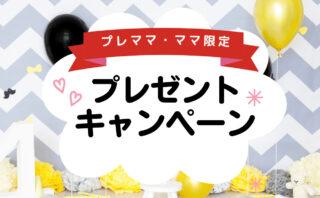


コメント